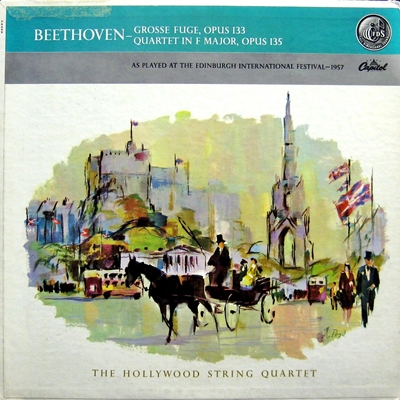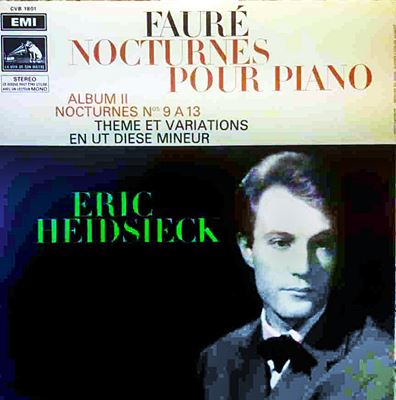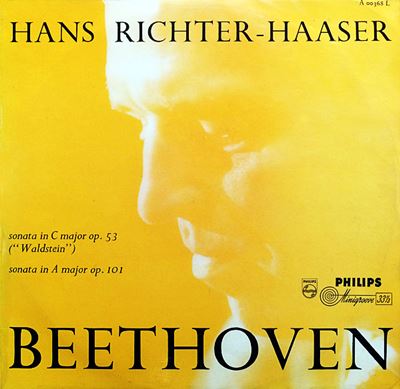Home|リリー・クラウス(Lili Kraus)|モーツァルト:ピアノ三重奏曲第6番 ト長調 K.564
モーツァルト:ピアノ三重奏曲第6番 ト長調 K.564
(P)リリー・クラウス (Vn)ウィリー・ボスコフスキー (vc)ニコラウス・ヒューブナー 1954年10月録音
Mozart:Piano Trio in G major, K.564 [1.Allegro]
Mozart:Piano Trio in G major, K.564 [2.Andante]
Mozart:Piano Trio in G major, K.564 [3.Allegrotto]
モーツァルト:ピアノ三重奏曲の概要

しかし、モーツァルトは自分自身もその様にとらえていながら、出来上がった作品を見ればピアノとヴァイオリンは同等のパートナーとして旋律と伴奏を分け合っています。さすがに、チェロはバス楽器として低声部を支えることに徹していますが、それでも時々ハッとするような重要なメロディラインを担当したりもします。
ディヴェルティメント(ピアノ三重奏曲第1番) 変ロ長調 K.254
モーツァルトは控えめに「ディヴェルティメント」と記しているのですが、本質的にはピアノ三重奏曲ですので、今日では一般的には「ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 K.254」と記されることの方が多いです。
モーツァルトという人は基本が職業音楽家ですから、どこからか注文があったり、もしくは自らが演奏会を開くためか、つまりは何らかの需要があってはじめて作曲という行為を行います。ところが、この作品に関しては注文があった形跡もありませんし、何らかの演奏会で演奏された形跡もありません。
ですから、モーツァルトにしては珍しいことなのですが、おそらくは仲間内の楽しみのために書かれたものではないかと推測されています。
この作品でもヴァイオリンはそれなりの腕前は要求されますが、チェロに関して言えばバス楽器に徹していますので、これを削除してヴァイオリンソナタとして演奏してもほとんど不都合のない音楽になっています。さらに言えば、ヴァイオリンを削除しても音楽的損失はそれほど大きくはないように見えます。その意味では、「ピアノ三重奏曲≒伴奏つきピアノソナタ」と言う、この時代の常識に収まった作品です
モーツァルト自身は「ディヴェルティメント」と記した第1番を作曲してから、彼自身はこのジャンルから遠ざかります。ところが、1786年から1788年にかけて、おそらくは音楽愛好家の集まりで演奏することを目的として5曲もの三重奏曲が生み出されます。そして、それらは、伴奏つきのピアノソナタにしか過ぎなかった「K.254」とは異なって、三つの楽器の間で対話が交わされる三重奏曲へと進化してるのです。
ピアノ三重奏曲第2番 ト長調 K.496
おそらくは、ウィーン大学教授で植物学者であったジャカン家での集まりで演奏されることを目的として作曲されたものと推測されています。その意味では、三重奏曲「ケーゲルシュタット」K.498と兄弟関係にある作品です。
この作品は若い時代のK.254とは異なって、明らかにヴァイオリンとチェロ、そしてピアノの右手と左手の4声部が対等な思いを持って対話を交わしはじめています。もちろん、チェロはヴァイオリンと較べればかなり控えめですが、それでも「なくても良い」と言うことにはなりません。
また、この作品の第2楽章は、数あるモーツァルトの緩徐楽章の中でもその洗練と威厳において特筆すべき偉大さを持った音楽になっています。
ピアノ三重奏曲第3番 変ロ長調 K.502
K.496の三重奏曲の4ヶ月後に作曲されたこの作品はこのジャンルにおける最高傑作と言われています。
また、この作品が書かれた1786年という年は音楽的には輝かしい成果を残した年ではあったのですが、同時に嫌でいやで仕方なかったザルツブルグでの宮仕えを放り投げてウィーンにやってきたモーツァルトの輝かしい成功にかげりが見え始めた年でもあります。しかし、その成功の頂点から彼は一気に転げ落ちていくことになるのですが、それでもこの年はまだ「何とかやっていける」と高をくくっていた時代でもあります。
経済的観念の乏しいモーツァルト一家は成功の時にお金を蓄えるという考えもなく、1785年からフリーめーsんの友人に借金を頼むようになるのですが、それでもオペラで当てれば一気に挽回できると考えていた節があります。しかし、目の前にお金が必要な事情は変わらないわけですから、この86年という年はせっせと作曲をしては日銭を稼ぐ毎日だったようです。
そして、そんな日々の中からでも、こんな傑作がかけてしまうのがモーツァルトなのです。
この作品において、ピアノ三重奏曲は真に三つの楽器が対等の立場で協奏的に音楽を語りはじめます。そして、とりわけ素晴らしいのがここでも緩徐楽章です。
「ラルゲットの壮麗な美は、モーツァルトがほんとうに真のロマン主義者であったことを示している。 その晴れやかな旋律は、ある種のシューベルトの音楽を髣髴とさせるほどに長大、雄大で、後期のピアノ協奏曲の中に置いても場違いではないだろう。」(ロジャー・ヘルヤー)
ピアノ三重奏曲 ホ長調 第4番 K.542
「私の生まれつきの率直さに従って、あれこれと体裁を飾らず、本題そのものに入ります。もし、私に対して愛と友情をおもちになり、千ないし二千グルデンを一年か二年の期限で、適当な利子をとってご用立て下さるならば、それこそ私が仕事をして行くのに大助かりとなります!
せめて明日までに数百グルデンだけでも、お貸し下さるようお願いいたします。」
こんな借金の依頼に対する感謝の念として作曲されたのではないかと言われています。
1786年は音楽的には輝かしい成果を残した年なのですが、経済的には下降線を描き出し、それは翌87年になるとさらに悪化するのです。ですから、その苦境を脱するために彼はがむしゃらに音楽を書きます。しかし、がむしゃらに書いたからと言って決して音楽のクオリティが損なわれるわけではありません。
この作品もまた、第2楽章のメランコリックな旋律が実に魅力的です。
ピアノ三重奏曲 ハ長調 第5番 K.548
アインシュタインはこの作品のことを「古典派の勝利」と書きながらも、その文章をよく読んでみるとあまり評価していないことが分かります。
「血の気のうすい先駆者のような感じを与える。 これは古典的巨匠の作品であるが、三つの三重奏曲の傑作のような案出の『活気』を持たないし、また主題の密度もない。 ただアンダンテ・カンタービレだけが、その柔和な宗教性において無限に感動的なものを持っているばかりである。」
確かに、K.502やK.542のような色の濃いロマン的な雰囲気は後退しているので「血の気の薄い」となるのでしょうが、見方によってはその単純な構造からモーツァルト以外からは決して聞くことの出来なかった繊細な叙情性が聞こえてくることも否定できないのです。
一昔前はアインシュタインは絶対でしたが、時が流れれば多様な見方は生まれてきます。
例えばフランスの音楽学者、ジャン・ヴィクトル・オカールはこの作品のことを「これらの明るい作品にみられる透明で、浄化された、輝かしい性格は、すでに最後のモーツァルトなのである」と述べています。
ピアノ三重奏曲 ト長調 第6番 K.564
この最後の作品は、もとはピアノソナタとして作曲されたのではないかと言われています。それほどに、弦楽器は従属的な地位に貶められています。ですから、アインシュタイン先生の評価も至って低いものとなっています。
「プフベルクのための比類のない弦楽三重奏曲(K.563)からちょうど1カ月後に完成されたが、元来はピアノ・ソナタだったもので、明らかに「初心者用」である。 モーツァルト自身の「標準」に従えば、3つの楽器が一つの論証的役割を果さなければならないはずのピアノ三重奏曲の枠を、これは全然満たしていない。」
ただし、この作品はかなりの確率で、仲間内で演奏を楽しむために急遽作られた可能性が高いです。その場限りの楽しみのために作った音楽を演奏会のために本気で作曲した作品と較べて、後世の人間があれこれ言うのは間違っているのかもしれません。
しかし、そうであっても、やはりモーツァルトはモーツァルトです。
アンダンテ楽章では魅力的な主題を三つの楽器が交互に演奏していくのですが、実に楽しげではないですか。
ピアノ三重奏曲 ニ短調 K.442
この作品は別々の起源を持った3つの断片楽章をもとにシュタードラーによって補筆完成されたものです。
シュタードラーはこれ以外にもピアノとバイオリンのための幾つかの作品(K.372・,K396・K402・K403)を補筆完成させていますが、おそらくはコンスタンツェの要望によるものだろうと推測されています。
第1楽章は約三分の一、残りの二つの楽章は半分程度がモーツァルト自身の手になるオリジナルです。
ただし、第3楽章は最近の研究で1778年以降に書かれたものと思われるようになり、それが事実ならばこのジャンルにおける(正確を記すならば、現存する)最後の作品と言うことになります。
ウィーンゆかりの作曲家の作品を集中的に録音
ボスコフスキーは50年代の中頃に、ピアニストとのリリー・クラウスやウィーンフィルの気心の知れた連中を集めて、ウィーンゆかりの作曲家の作品を集中的に録音しています。そのラインナップは、確認できただけで以下の通りです。
- モーツァルト:ヴァイオリンソナタ(ほぼ全集) (P)リリー・クラウス (Vn)ウィリー・ボスコフスキー 1954年~1957年録音
- モーツァルト:ピアノ三重奏曲全集 (P)リリー・クラウス (Vn)ボスコフスキー (vc)ニコラス・ヒューブナー 1954年録音
- モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番・20番 (con)ウィリー・ボスコフスキー (p)リリー・クラウス ウィーン・コンツェルトハウス室内管弦楽団 1955年録音
- ベートーベン:ヴァイオリンソナタ全集 (P)リリー・クラウス (Vn)ウィリー・ボスコフスキー 1955年録音
- シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第1番、第2番、第3番 (P)リリー・クラウス (Vn)ウィリー・ボスコフスキー 1957年録音
ウィーンフィルというのはいうまでもなくウィーン国立歌劇場のオケのメンバーによって自主的に運営されている団体です。そして、母体であるウィーン国立歌劇場というのは、9月から翌年6月までのシーズンでクリスマスの日しか休まないという世界で最も勤勉な歌劇場です。もちろん、オケのメンバーは交代で歌劇場で演奏するのですが、それでも激務であることは変わりはなく、その合間を縫ってこれだけの録音を残したことには驚きを感じます。
ただ、そういう事情が背景にあるためか、その演奏はスコアを徹底的に読み込んで新しい解釈や発見を世に問うというものではなく、我らが街の、我らが作曲家の作品を、我らの先輩達が演奏してきた流儀で演奏しています。そして、それが、「伝統とは怠惰の別名」と喝破したマーラーの言葉を思い出してしまうような場面があちこちにあります。
要は、緩いんですね。(^^v
ですから、モーツァルトやシューベルトはまだしも、ベートーベンのヴァイオリンソナタに関してはほとんど話題になることもなく、忘れ去られてしまった録音になっています。こう言い切っても、ほぼ間違いないでしょう。
しかし、考えてみれば、ベートーベンのヴァイオリンソナタというのは、そのほとんどがベートーベンの初期作品です。特に、作品12の3作品などははっきりとハイドンやモーツァルトの影響が刻み込まれています。4番から8番にしても、それらは「エロイカ以前」の作品です。あまり眦決して演奏するよりは、こういう緩めの風情でのんびり聞くのも悪くはないのです。
そう言えば、この作品の決定盤ともいうべきオイストラフ&オポーリン盤について、こんな恐れ多いことを書いたことがあります。
「仕事の仕上がりが完璧であればあるほど、ベートーベンの若書きゆえの弱さみたいなものがあぶり出されていくような気もするのです。」
ほとんど言いがかりのような物言いなのですが、この緩い演奏を聴くことで、再びそれが言いがかりとも言い切れないことに音楽の難しさを垣間見たような気がします。
なお、最後に録音に関する情報を一つ。
このボスコフスキーとクラウスを核とした一連の録音は、前半はウィーンで、後半はパリで行われています。このベートーベンのヴァイオリンソナタに関していえば、1番から5番、そして8番がウィーンで行われ、録音を担当したのはAntoine Duhamel(アントワーヌ・デュアメル)です。
アントワーヌ・デュアメルと言えばフランスの作曲家、音楽学者として知られているのですが、この頃はAndre Charlin(アンドレ・シャルラン)のもとで録音エンジニアをしていたのですね。
そして、注目すべきは後半のパリでの録音で、こちらはフランスの伝説的名ンジニア、アンドレ・シャルランが担当しています。
雰囲気的には54年から55年にかけてはAntoine Duhamel、56年から57年にかけてははAndre Charlinが担当したようです。
Antoine Duhamelの録音はどちらかと言えば常識的な音のとり方ですが、Andre Charlinの方はさすがの音作りです。ピアノとヴァイオリンという二つの楽器が対等に一つの空間で鳴り響いている姿を実にうまくすくい取っています。こういうのを聞くと、編成の小さな室内楽ではモノラル録音であることはほとんどハンデにはならないことを教えられます。
この演奏を評価してください。
- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2
- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4
- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6
- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8
- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10
- 件名は変更しないでください。
- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。
よせられたコメント
2018-04-14:せいの
- だいぶ前に新星堂企画のCDを持っていたのですが、どこにいったのかなくしてしまったので、この音源が入手でき、懐かしく聴いています。ありがとうございます。
リリー・クラウスのピアノはスケールが大きくて、ピアノ・ソナタも彼女の演奏は愛聴盤です。ここでもスケール感のある演奏をしていてわたしの好みです。
一方で、ボスコフスキーのヴァイオリンが「無難」な感じで物足りなさを感じてしまいます。もっとも、その感覚は個人的な好みの問題なので、普遍性はないと思います。ウィーン風の典雅な演奏だし、評価する方もいることでしょう。
同時期のウィーンで活躍したヴァイオリニストならワルター・バリリの演奏が好みなので、リリー・クラウスとワルター・バリリでヴァイオリン・ソナタや三重奏曲をやってくれていたらなあ・・・などど考えて、その組み合わせならどんな演奏になっただろうと妄想をしたりして楽しんでいます^^。
2023-10-19:クライバーファン
- 高橋英郎「モーツァルト366日」という本を古本で買ってこの曲に巡り合いました。この本は、モーツァルト礼賛一色で、ベートーヴェン批判が書かれていて読んでいてとても腹立たしい本です。
そしてこの曲を聞いてみましたが、なるほど、第2楽章などの静かな部分なんかは深い味わいがると思ったものです。
ただ、私の曲を理解する能力の欠如によるのだと思いますが、一回聞いて大いに楽しむというわけにはいきませんでした。ベートーヴェンのピアノ・トリオ第1番の方が、そういう意味では分かりやすい曲です。
ところで、ユング君のボザール・トリオの解説で「それに、ピアノ・トリオというジャンルはただでさえクラシック音楽の「裏街道」である室内楽の世界においても、さらに「裏街道」の世界です。」と書かれていて衝撃を受けました。ピアノ・トリオって裏街道中の裏街道なんですか! でも半分ぐらいは同意したい気になります、特にこういう曲を聞くと。
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-02-28]
グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)
[2026-02-25]
ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-22]
ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)
[2026-02-18]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)
[2026-02-16]
スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)
[2026-02-12]
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)
[2026-02-10]
フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-02-08]
ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-06]
ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)
[2026-02-02]
ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)