Home| 作曲家で選ぶ | GRIEG
彼はそこで、作曲法やピアノ奏法のみでなく、ドイツ方式の堅固な音楽語法を学び取る。
1862年に音楽院を卒業したグリーグは、ベルゲンにおいてピアニストおよび作曲家として正式にデビューを行う。その後、ノルウェー音楽の確立と普及に意欲を燃やすノルドラークと親交を結び、二人が中心となってオイテルペ協会を設立してノルウェーの作品を活発に演奏するようになる。しかし、その活動も1866年のノルドラークの死で終わりを迎え、その後はオスロを活動の拠点として音楽院副院長や指揮者としての活動を行う。
このオスロ時代に、声楽家のニーナと結婚、またピアノ協奏曲などの作品がリストから賞賛され作曲家としての自信も深めていく。
1873年、オスロを離れた後も、外国への演奏旅行がしばしば行われて国際的な名声は高まっていく。しかし、生来病弱だった彼は、この頃から体調を崩すことが多くなり、夏はベルゲンの奥地にあるフィヨルド沿いに小屋を建てて作曲活動を行うようになる。
1885年にはベルゲンの校外に永住のための家を建て移り住み、98年にはベルゲンで音楽祭を行い(今日のベルゲン音楽祭の前身)その中心的な人物として活躍するも、体調はますます悪化していく。
そして、1905年にはほとんどが病院での生活なり、1907年9月4日にベルゲンの病院で生涯を閉じる。
グリーグは専門家筋からはあまり高く評価されない人です。その辺はほぼ同じ時代を生きたリムスキー・コルサコフ(1844〜1908)などともよく似ています。
「いつまでもシェエラザードでもないだろう」と言われるとよく似て、「いつまでもグリーグのピアノ協奏曲でもばいだろう」と言うわけです。つまり、華やかで耳あたりはいいのだが、どうも中味的に今ひとつの感があるという訳なのでしょう。ユング君も、このような言い方はそれほど不当なものだとは思いませんが、たまに彼の作品を聞くとやはり気分がいいのも事実です。
グリーグと言えば、このピアノ協奏曲とペール・ギュント(それも組曲の方)がダントツで有名ですが、その次となるととたんに詰まってしまいます。
ピアノ協奏曲は、第1楽章の出だしの部分を聴けば、それがグリーグのピアノ協奏曲だと知らない人でも、「あぁ、あの曲か!」とピントくるほどポピュラーです。ペール・ギュントも、その全曲を聴いた人はほとんどいないでしょうが、「朝」は小学校の音楽の鑑賞曲にもなっていただけにほとんどの人が知っているメロディーです。しかし、それ以外のグリーグの作品となるとすぐに思い出すのは困難です。
また、北欧の音楽家という看板も、後にシベリウスが現れると何となく影が薄くなります。
どこか中途半端なところが否定しきれないのがグリーグという人です。
しかし、近年になって彼の膨大なピアノ曲が録音され、また歌曲集なども活発に取り上げられるようになってきましたおかげで、ペール・ギュントとピアノ協奏曲だけの人でない、グリーグの全貌が少しずつ一般の人にも明らかになってきました。もしかしたら、そのような動きのなかで彼への評価もいくらかは変わってくるのかもしれません。
しかし、そのような新しい動きにあまり敏感に反応し切れていないユング君には、これ以上何も言う資格がありません。
現代音楽が全く不調ななかでそれなりに元気さを保っているのが北欧圏です。そう言う北欧圏での活発な動きのなかで、シベリウス以降の多くの作曲家に光が当てられ、その流れのなかでグリーグやニールセンなどの有名ではあっても「限定的な評価」しかされてこなかった人々をもう一度全面的に見なそうという動きがあるようです。
しかし、そのような動きの持つ幅の広さと厚みにユング君自身がたじろいでしまっているのも事実で、今は意識的に回避しているようなところがあります。
でも、いつまでも逃げているわけにもいかず、どこかで腹をくくって踏み込まなくっちゃいけないんだろうな、と思いつつも入り口でぐずぐずしているのが今のユング君ですから、言えるのはここまでです。
GRIEG
<ノルウェー:1843〜1907>
経歴
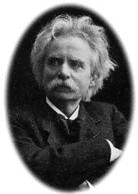
彼はそこで、作曲法やピアノ奏法のみでなく、ドイツ方式の堅固な音楽語法を学び取る。
1862年に音楽院を卒業したグリーグは、ベルゲンにおいてピアニストおよび作曲家として正式にデビューを行う。その後、ノルウェー音楽の確立と普及に意欲を燃やすノルドラークと親交を結び、二人が中心となってオイテルペ協会を設立してノルウェーの作品を活発に演奏するようになる。しかし、その活動も1866年のノルドラークの死で終わりを迎え、その後はオスロを活動の拠点として音楽院副院長や指揮者としての活動を行う。
このオスロ時代に、声楽家のニーナと結婚、またピアノ協奏曲などの作品がリストから賞賛され作曲家としての自信も深めていく。
1873年、オスロを離れた後も、外国への演奏旅行がしばしば行われて国際的な名声は高まっていく。しかし、生来病弱だった彼は、この頃から体調を崩すことが多くなり、夏はベルゲンの奥地にあるフィヨルド沿いに小屋を建てて作曲活動を行うようになる。
1885年にはベルゲンの校外に永住のための家を建て移り住み、98年にはベルゲンで音楽祭を行い(今日のベルゲン音楽祭の前身)その中心的な人物として活躍するも、体調はますます悪化していく。
そして、1905年にはほとんどが病院での生活なり、1907年9月4日にベルゲンの病院で生涯を閉じる。
ユング君の一言
グリーグは専門家筋からはあまり高く評価されない人です。その辺はほぼ同じ時代を生きたリムスキー・コルサコフ(1844〜1908)などともよく似ています。
「いつまでもシェエラザードでもないだろう」と言われるとよく似て、「いつまでもグリーグのピアノ協奏曲でもばいだろう」と言うわけです。つまり、華やかで耳あたりはいいのだが、どうも中味的に今ひとつの感があるという訳なのでしょう。ユング君も、このような言い方はそれほど不当なものだとは思いませんが、たまに彼の作品を聞くとやはり気分がいいのも事実です。
グリーグと言えば、このピアノ協奏曲とペール・ギュント(それも組曲の方)がダントツで有名ですが、その次となるととたんに詰まってしまいます。
ピアノ協奏曲は、第1楽章の出だしの部分を聴けば、それがグリーグのピアノ協奏曲だと知らない人でも、「あぁ、あの曲か!」とピントくるほどポピュラーです。ペール・ギュントも、その全曲を聴いた人はほとんどいないでしょうが、「朝」は小学校の音楽の鑑賞曲にもなっていただけにほとんどの人が知っているメロディーです。しかし、それ以外のグリーグの作品となるとすぐに思い出すのは困難です。
また、北欧の音楽家という看板も、後にシベリウスが現れると何となく影が薄くなります。
どこか中途半端なところが否定しきれないのがグリーグという人です。
しかし、近年になって彼の膨大なピアノ曲が録音され、また歌曲集なども活発に取り上げられるようになってきましたおかげで、ペール・ギュントとピアノ協奏曲だけの人でない、グリーグの全貌が少しずつ一般の人にも明らかになってきました。もしかしたら、そのような動きのなかで彼への評価もいくらかは変わってくるのかもしれません。
しかし、そのような新しい動きにあまり敏感に反応し切れていないユング君には、これ以上何も言う資格がありません。
現代音楽が全く不調ななかでそれなりに元気さを保っているのが北欧圏です。そう言う北欧圏での活発な動きのなかで、シベリウス以降の多くの作曲家に光が当てられ、その流れのなかでグリーグやニールセンなどの有名ではあっても「限定的な評価」しかされてこなかった人々をもう一度全面的に見なそうという動きがあるようです。
しかし、そのような動きの持つ幅の広さと厚みにユング君自身がたじろいでしまっているのも事実で、今は意識的に回避しているようなところがあります。
でも、いつまでも逃げているわけにもいかず、どこかで腹をくくって踏み込まなくっちゃいけないんだろうな、と思いつつも入り口でぐずぐずしているのが今のユング君ですから、言えるのはここまでです。
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-02-10]
フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-02-08]
ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-06]
ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)
[2026-02-02]
ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)
[2026-01-31]
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)
[2026-01-27]
ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)
[2026-01-25]
J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)
[2026-01-21]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)
[2026-01-19]
フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-01-16]
ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)







