Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1954年2月26~28日
Mendelsshon:交響曲第4番「イタリア」 「第1楽章」
Mendelsshon:交響曲第4番「イタリア」 「第2楽章」
Mendelsshon:交響曲第4番「イタリア」 「第3楽章」
Mendelsshon:交響曲第4番「イタリア」 「第4楽章」
弾むリズムとほの暗いメロディ
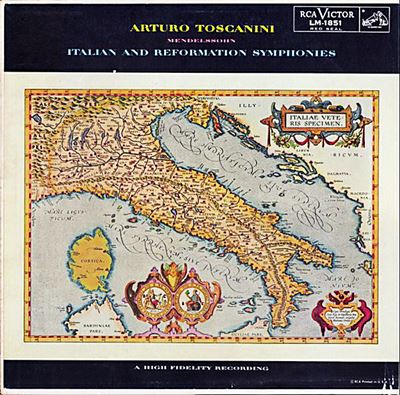
この作品はその名の通り1830年から31年にかけてのイタリア旅行の最中にインスピレーションを得てイタリアの地で作曲されました。しかし、旅行中に完成することはなく、ロンドンのフィルハーモニア協会からの依頼を受けて1833年にようやく完成させています。
初演は同年の5月13日に自らの指揮で初演を行い大成功をおさめるのですが、メンデルスゾーン自身は不満を感じたようで、その後38年に大規模な改訂を行っています。ただ、その改訂もメンデルゾーン自身を満足させるものではなくて、結局彼は死ぬまでこの作品のスコアを手元に置いて改訂を続けました。そのため、現在では問題が残されたままの改訂版ではなくて、それなりに仕上がった33年版を用いることが一般的です。
作品の特徴は弾むようなリズムがもたらす躍動感と、短調のメロディが不思議な融合を見せている点にあります。
通常この作品は「イタリア」という名が示すように、明るい陽光を連想させる音楽をイメージするのですが、実態は第2楽章と最終楽章が短調で書かれていて、ほの暗い情感を醸し出しています。明るさ一辺倒のように見える第1楽章でも、中間部は短調で書かれています。
しかし、音楽は常に細かく揺れ動き、とりわけ最終楽章は「サルタレロ」と呼ばれるイタリア舞曲のリズムが全編を貫いていて、実に不思議な感覚を味わうことができます。
何もつけくわえる必要のない歴史的録音
メンデルスゾーンの「イタリア」とレスピーギの「ローマの松」の録音だけあれば、それ以外の全ての業績が消えて無くなったとしてもトスカニーニの名前は歴史に刻み込まれるだろう。誰の言葉かは失念しましたが、まさにその通りで、この歴史的金字塔とも言うべきこの録音を前にして今さらつけくわえる言葉はありません。
ただ、蛇足を承知で一言つけ加えれば、この録音はトスカニーニ引退の引き金となったあの歴史的事件(1954年4月4日)のわずか1ヶ月ほど前の事(1954年2月26〜28日)だと言うことは知っておいていいことでしょう。
最近、この歴史的事件をリアルに収録したCDがリリースされました。そのCDの売りとして次のような言葉が付与されています。
「このディスクはトスカニーニの生涯最後の演奏会をすべて収録したものである。この演奏会の「タンホイザー」序曲とバッカナーレの途中、トスカニーニは記憶障害を起こし、そこで演奏が中断されるというショッキングな出来事が起きたため、トスカニーニは引退を決意したと言われている。
この演奏会はよく知られているようにステレオでも収録されているが、そのステレオ版にはその空白の時間が収められていない。しかし、ベン・グラウアーのアナウンスにより生中継されたラジオ放送は、音声そのものはモノーラルではあるが、この空白の時間が克明に記されている。それは突然襲ってくる。長い沈黙のあと、グラウアーが "Due to operation difficulties, there is a temporary pause of our broadcast from Carnegie Hall" (技術上の不手際により、ただいまカーネギー・ホールからの放送が中断しています)と言い、一瞬だが調整室のスタッフが凍り付いているような緊張感も伝わってくる。
最近考えるのは、この記憶喪失は突然やってきたものなのか?ということです。一般的には突然の出来事にショックを受けたトスカニーニはこれをきっかけにすっぱり引退をしたことになっているのですが、果たしてそうなのでしょうか?
音楽に己の人生をかけてきたこの男が、たかが一度のアクシデントでそれを捨て去ってしまうものでしょうか?そうではなくて、このような記憶障害がたびたび彼を襲っていて、いつか演奏会でそれが原因となって大失敗をしでかすのではないかという恐れを抱き続けてきたのではないでしょうか?
「われわれは予期せぬものにつまずいたときよりも、予期したことが起こったときに、驚くものである。」(エリック・ホッファー)
もしそうだとすれば、その様な恐れを抱きながらも最後の最後まで指揮活動を続けた事に、トスカニーニという男の凄味と執念を感じます。そして、逆説的な言い方になりますが、そう言う執念の産物がこのイタリアの録音ではないかと思うのです。
とてつもない集中力によって構築された壮麗なシンフォニーを聴くとき、この想像はそれほど外れてはいないと思うのですが、いかがなものでしょうか。
この演奏を評価してください。
- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2
- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4
- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6
- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8
- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10
- 件名は変更しないでください。
- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。
よせられたコメント
2012-11-05:クラシック大好き
- メンデルスゾーンは屈託がなく豊かで好きです。いい意味でメロディーやハーモニーに「無理」がないことも特徴です。そういう代表曲として「イタリア」やヴァイオリン協奏曲を好んで聴きます。このトスカニーニの演奏も大好きです。とくに両端楽章のほとばしるような若々しさには胸を打たれます。トスカニーニはフルトヴェングラーと違い、演奏に関してあれこれ深刻に思い悩むことなく、多くの曲を比較的ストレートに解釈していたのではないでしょうか。もちろん空虚や表面的なものではなく、よく考えられた解釈だと思います。この曲もトスカニーニにぴったりだと思います。
2014-10-29:ろば
- この歴史的名演を拝聴して考えたことは、メンデルスゾーンには曖昧な態度で接してはいけないのかな、ということでした。
超強引な態度でもって臨まないと、メンデルスゾーンの悩みのるつぼに引き込まれて平板な演奏になってしまうのかなあと、漠然と感じた次第です。
2024-12-21:Ken1954
- 世紀の名演と言われてきたが、改めてヘッドフォンでしっかり聴いてみると確かに・・・。一流指揮者の一流オケの演奏が目白押しだが、自分がその演奏会場にいる感じ方で情熱と気迫がほとばしるのは数例。絵画、舞台、映画、そして食品にも通じるのだが?作者の存在感、?作品のテーマ・主張,?作品の構成(素材の在り方の含め)?作品の活かし方(表現、運用)などの多面的切り口で時代を超えて群を抜いた演奏である。トスカニーニがイタリア人であるからでなく、本人の才能であり、イタリア現地での真の身についた身体知(暗黙知)をもつ国際人ならばその理由を説明できない何かを感じるのであろう。
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-02-10]
フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-02-08]
ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-06]
ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)
[2026-02-02]
ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)
[2026-01-31]
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)
[2026-01-27]
ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)
[2026-01-25]
J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)
[2026-01-21]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)
[2026-01-19]
フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-01-16]
ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)







